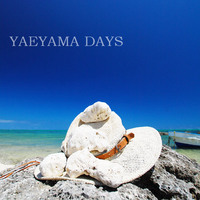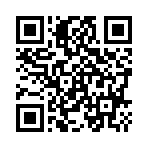2007年04月24日
【更新】津波にそなえる
自分が津波におそわれるかもしれない、
という実感はありますか?
去る4月20日、宮古島で震度3の地震が発生。宮古島・八重山地方で〇・五メートルの津波の恐れがあるとして、気象庁から津波注意報が出されました。
幸い大事には至りませんでしたが、揺れは小さかったここ石垣島でも、津波注意報の広報車がはしり、一時は騒然となりました。
気象庁にれば、震源地は宮古島北西沖、石垣島の北東180キロ付近で、震源の深さは約20キロ。マグニチュード(M)6.7と推定。震源地は沖縄トラフの中軸にあたり、群発地震活動が活発な地域だそうです。
僕が住む石垣島には、確実度の高い活断層こそ知られていませんが、近海にはいくつかの海底活断層があります。石垣島の北沖に1本、北東沖の多良間島との間に2本、近い南沖に数本。これらは長い間沈黙してはいますが、常識的に「阪神間には地震などない」と誰もが思い込んでいた矢先に起きた阪神・淡路大震災の例を出すまでもなく、どの海底活断層もいつ動き出しても不思議はありません。
さらに、西表島から与那国島にかけて多くの海底活断層が存在しているそうす。
過去にも、大きな津波がありました。「明和の大津波」です。
1771年4月24日(旧暦3月10日)午前8時頃、石垣島の南南東35km付近でマグニチュード7.4の地震が発生。震度4程度で、地震の揺れによる被害はほとんどなかったようですが、この地震により大規模な津波が発生し、八重山に甚大な被害をもたらしました。
津波の遡上は現在の石垣島市街地の大部分(おおむね4号線から空港より低い地域)に及び、死者の数は実に八重山で約9000人、宮古島で約2000人。当時の八重山の人口3万人弱の1/3が犠牲になり、飢饉や疫病などにより以後100年にわたり人口減少がつづきました。
ひとごとではない。このようなことが、いつ起きてもおかしくありません。
四方を海に囲まれた島ですから、遠方で発生した津波の影響も受けうる。
石垣島は「常に津波の危険性にさらされている」といっても過言ではない環境です。
それなのに、僕には津波に関する知識がまったくといっていいほどなく、いざというときどうやって身を守ったらいいのかわかりませんでした。
阪神大震災後、常に用意していた非常用避難用品も、引越しを機に処分していまい、防災意識も薄れていたのが正直なところです。
そこで、「津波は来るのだ」ということを前提に、自分なりの避難メモをつくりました。
阪神大震災で三ヶ月あまりの避難生活を経験した者として、ここに公開します。
津波をあまく見ていたことに気づくとともに、誤解していたことも意外に多く、あやうく命を落としかねないところでした。
ぜひ、ご一読ください。
あくまで個人的なメモですが、あなたの役に立つこともあるかと思います。
という実感はありますか?
去る4月20日、宮古島で震度3の地震が発生。宮古島・八重山地方で〇・五メートルの津波の恐れがあるとして、気象庁から津波注意報が出されました。
幸い大事には至りませんでしたが、揺れは小さかったここ石垣島でも、津波注意報の広報車がはしり、一時は騒然となりました。
気象庁にれば、震源地は宮古島北西沖、石垣島の北東180キロ付近で、震源の深さは約20キロ。マグニチュード(M)6.7と推定。震源地は沖縄トラフの中軸にあたり、群発地震活動が活発な地域だそうです。
僕が住む石垣島には、確実度の高い活断層こそ知られていませんが、近海にはいくつかの海底活断層があります。石垣島の北沖に1本、北東沖の多良間島との間に2本、近い南沖に数本。これらは長い間沈黙してはいますが、常識的に「阪神間には地震などない」と誰もが思い込んでいた矢先に起きた阪神・淡路大震災の例を出すまでもなく、どの海底活断層もいつ動き出しても不思議はありません。
さらに、西表島から与那国島にかけて多くの海底活断層が存在しているそうす。
過去にも、大きな津波がありました。「明和の大津波」です。
1771年4月24日(旧暦3月10日)午前8時頃、石垣島の南南東35km付近でマグニチュード7.4の地震が発生。震度4程度で、地震の揺れによる被害はほとんどなかったようですが、この地震により大規模な津波が発生し、八重山に甚大な被害をもたらしました。
津波の遡上は現在の石垣島市街地の大部分(おおむね4号線から空港より低い地域)に及び、死者の数は実に八重山で約9000人、宮古島で約2000人。当時の八重山の人口3万人弱の1/3が犠牲になり、飢饉や疫病などにより以後100年にわたり人口減少がつづきました。
ひとごとではない。このようなことが、いつ起きてもおかしくありません。
四方を海に囲まれた島ですから、遠方で発生した津波の影響も受けうる。
石垣島は「常に津波の危険性にさらされている」といっても過言ではない環境です。
それなのに、僕には津波に関する知識がまったくといっていいほどなく、いざというときどうやって身を守ったらいいのかわかりませんでした。
阪神大震災後、常に用意していた非常用避難用品も、引越しを機に処分していまい、防災意識も薄れていたのが正直なところです。
そこで、「津波は来るのだ」ということを前提に、自分なりの避難メモをつくりました。
阪神大震災で三ヶ月あまりの避難生活を経験した者として、ここに公開します。
津波をあまく見ていたことに気づくとともに、誤解していたことも意外に多く、あやうく命を落としかねないところでした。
ぜひ、ご一読ください。
あくまで個人的なメモですが、あなたの役に立つこともあるかと思います。
■海岸で地震を感じたら、ただちに高台など安全な場所に避難する。
・津波警報・津波注意報より早く津波が来る場合もある。(例:奥尻島)
・弱い地震でも大きな津波が来る場合もある。(例:津波地震)
・潮が急に大きくひいたら津波が来るというだけではない。いきなり高波が来る津波もある。
・晴れた日は津波は来ない、というのは誤り。天候に関係なく津波は発生する。
・海岸から海上の津波を目で確認することはまず不可能。
・予想外に速い。津波に気づいてから逃げ始めても、逃げ切ることは不可能と考えるべき。
・地震以外の原因で発生する津波もある。津波警報・津波注意報が出たら、すぐ避難。
・津波警報の2mで木造家屋は全壊、1mで半壊の威力があるので、あなどるな。
・過去事例から、石垣島市街地における安全ラインの目安は、現在の4号線から空港より高い場所。
■よりリスクのすくない避難をこころがける。
・津波に巻き込まれないことが第一。日頃から避難場所と避難経路を考え、具体的に頭に入れておく。
・できるだけ直線的に高台をめざす経路で避難したい。
・津波被害者の死因の多くは溺死ではなく打撲。入り組んだ路地は避ける。
・海岸線と垂直な縦波だけでなく、路地をまわりこんでくる横波も同時にある。
・津波は港などⅤ字形湾奥で強くなり、川を遡上するため、宮良湾やシード線は危険。
・自動車での避難は、パニック渋滞に巻き込まれる危険性あり。避難は徒歩で。
・自動車はエンジンを止め、キーをつけたまま停め、徒歩で避難。
・身近な動物(ヤギ、牛、犬、猫など)は逃げ場所を本能的に知っている。彼らの動きにもヒントがある。
■高台への避難が間に合わない場合、鉄筋コンクリート建物の三階より上に避難する。
・津波に巻き込まれることを前提にした緊急手段。世界の事例ではこれで助かっている人が多い。
■避難したら12~24時間は注意が必要。
・津波は何回も繰り返し襲ってくるもの。
・津波警報・津波注意報などが解除されるまで家には戻らない。海岸に近づなかい。
・津波は最初の第1波が最大とは限らない。むしろ2波、3波が強い場合がある。
・第1波の後、数時間の間隔をおいて2波、3波とやってくることがある。
・正しい情報をテレビ・ラジオ・広報車などから把握する。
・一般人で津波に詳しい人間などまずいない。決してデマにまどわされないように。
■夜中・早朝の災害への対応
・枕元に、避難袋と靴(島ぞうり不可)をおいておく。
・緊急時にすぐ避難を開始できるように。
・泥酔しない。(酔っていると思考力・運動能力が落ちる)
【参考】地震発生の際の心得
・落ち着いて身の安全を確保することが第一。
・多くの場合、揺れは1分程度。屋内にいる場合、あわてて外に飛び出さない。
・まずドアを開けて避難口を確保。トイレ及び入浴時も同様。
・すばやく火の始末。最もこわい二次災害は火災。
・避難は電気・ガスの元栓をしめて。
・お家から出るとき、割れた食器等で足を怪我しないよう注意。
・避難は徒歩で。島ぞうりではなく靴。動きやすい服装、持ち物は最小限で。
・避難の際、エレベーターは使わない。停電したらとじこめられる。
・バッグや座布団などで頭を保護する。
・危険な場所は、狭い路地、塀際、自動販売機、電柱、看板、川べり、がけ等。
・当座の避難場所は、公園や空き地など広い場所。
・自動車はエンジンを止め、キーをつけたまま、ロックせずに停める。
・ガスもれの可能性があるため、煙草の火はつけない。
・地盤がゆるみ建物等も損傷が考えられるため、余震がむしろ非常に危険。
【参考】僕の避難袋のなかみリスト
□リュック(両手が使えるよう背負うタイプ)
□貴重品類…現金、預金通帳、印鑑、クレジットカード、免許証・健康保険証の写しなど
□応急医薬品…消毒液、包帯、女性用ナプキン(止血に使用)、バンドエイド、薬の処方箋など
□携帯ラジオ(予備電池)
□懐中電灯(予備電池)
□携帯電話(充電装置)直後は使えないことを覚悟の上で
□飲料水は1人1日3リットル目安
□第1次非常食…乾パン、栄養補助食品など火を通さなくても食べられるもの
□(第2次非常食…缶詰、凍結乾燥食品、レトルト食品、真空パックなど保存がきくもの)
□衣類…下着、靴下、シャツ、靴、タオル
□軍手及び革グローブ
□ナイフ、缶きり、ハサミ
□ティッシュ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ
□歯磨きセット、ドライシャンプー
□ビニール袋、ポリ袋
□メガネ予備
□家屋や車の合鍵
□油性ペン
□使い捨てカメラ
【参考】津波対策に役立つページ
▼津波防災マニュアル(石垣島地方防災連絡会・平成16年3月)
http://www.okinawa-jma.go.jp/ishigaki/tmanual/home.htm
▼石垣市・津波浸水予測区域・津波避難場所及び津波避難経路
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/100000/100100/tunamidata/Yosoku.htm
▼石垣市街地の8カ所に「津波避難ビル」の標識
http://www.y-mainichi.co.jp/?action_article_show=true&article_id=5706
▼竹富町・津波浸水予測区域・津波避難場所及び津波避難経路
http://www.town.taketomi.okinawa.jp/gyousei/bousai/bousaihinanbasyo/yosoku.htm
▼Wikipedia:津波(津波に関する基本知識)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E6%B3%A2#.E9.80.9F.E3.81.95
▼琉球大学理学部中村衛研究室(明和の大津波に関する研究)
http://seis.sci.u-ryukyu.ac.jp/hazard/EQ/1771yaeyama/
▼石垣島地方気象台
http://www.okinawa-jma.go.jp/ishigaki/home.htm
▼沖縄気象台
http://www.okinawa-jma.go.jp/
▼気象庁:地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
・津波警報・津波注意報より早く津波が来る場合もある。(例:奥尻島)
・弱い地震でも大きな津波が来る場合もある。(例:津波地震)
・潮が急に大きくひいたら津波が来るというだけではない。いきなり高波が来る津波もある。
・晴れた日は津波は来ない、というのは誤り。天候に関係なく津波は発生する。
・海岸から海上の津波を目で確認することはまず不可能。
・予想外に速い。津波に気づいてから逃げ始めても、逃げ切ることは不可能と考えるべき。
・地震以外の原因で発生する津波もある。津波警報・津波注意報が出たら、すぐ避難。
・津波警報の2mで木造家屋は全壊、1mで半壊の威力があるので、あなどるな。
・過去事例から、石垣島市街地における安全ラインの目安は、現在の4号線から空港より高い場所。
■よりリスクのすくない避難をこころがける。
・津波に巻き込まれないことが第一。日頃から避難場所と避難経路を考え、具体的に頭に入れておく。
・できるだけ直線的に高台をめざす経路で避難したい。
・津波被害者の死因の多くは溺死ではなく打撲。入り組んだ路地は避ける。
・海岸線と垂直な縦波だけでなく、路地をまわりこんでくる横波も同時にある。
・津波は港などⅤ字形湾奥で強くなり、川を遡上するため、宮良湾やシード線は危険。
・自動車での避難は、パニック渋滞に巻き込まれる危険性あり。避難は徒歩で。
・自動車はエンジンを止め、キーをつけたまま停め、徒歩で避難。
・身近な動物(ヤギ、牛、犬、猫など)は逃げ場所を本能的に知っている。彼らの動きにもヒントがある。
■高台への避難が間に合わない場合、鉄筋コンクリート建物の三階より上に避難する。
・津波に巻き込まれることを前提にした緊急手段。世界の事例ではこれで助かっている人が多い。
■避難したら12~24時間は注意が必要。
・津波は何回も繰り返し襲ってくるもの。
・津波警報・津波注意報などが解除されるまで家には戻らない。海岸に近づなかい。
・津波は最初の第1波が最大とは限らない。むしろ2波、3波が強い場合がある。
・第1波の後、数時間の間隔をおいて2波、3波とやってくることがある。
・正しい情報をテレビ・ラジオ・広報車などから把握する。
・一般人で津波に詳しい人間などまずいない。決してデマにまどわされないように。
■夜中・早朝の災害への対応
・枕元に、避難袋と靴(島ぞうり不可)をおいておく。
・緊急時にすぐ避難を開始できるように。
・泥酔しない。(酔っていると思考力・運動能力が落ちる)
【参考】地震発生の際の心得
・落ち着いて身の安全を確保することが第一。
・多くの場合、揺れは1分程度。屋内にいる場合、あわてて外に飛び出さない。
・まずドアを開けて避難口を確保。トイレ及び入浴時も同様。
・すばやく火の始末。最もこわい二次災害は火災。
・避難は電気・ガスの元栓をしめて。
・お家から出るとき、割れた食器等で足を怪我しないよう注意。
・避難は徒歩で。島ぞうりではなく靴。動きやすい服装、持ち物は最小限で。
・避難の際、エレベーターは使わない。停電したらとじこめられる。
・バッグや座布団などで頭を保護する。
・危険な場所は、狭い路地、塀際、自動販売機、電柱、看板、川べり、がけ等。
・当座の避難場所は、公園や空き地など広い場所。
・自動車はエンジンを止め、キーをつけたまま、ロックせずに停める。
・ガスもれの可能性があるため、煙草の火はつけない。
・地盤がゆるみ建物等も損傷が考えられるため、余震がむしろ非常に危険。
【参考】僕の避難袋のなかみリスト
□リュック(両手が使えるよう背負うタイプ)
□貴重品類…現金、預金通帳、印鑑、クレジットカード、免許証・健康保険証の写しなど
□応急医薬品…消毒液、包帯、女性用ナプキン(止血に使用)、バンドエイド、薬の処方箋など
□携帯ラジオ(予備電池)
□懐中電灯(予備電池)
□携帯電話(充電装置)直後は使えないことを覚悟の上で
□飲料水は1人1日3リットル目安
□第1次非常食…乾パン、栄養補助食品など火を通さなくても食べられるもの
□(第2次非常食…缶詰、凍結乾燥食品、レトルト食品、真空パックなど保存がきくもの)
□衣類…下着、靴下、シャツ、靴、タオル
□軍手及び革グローブ
□ナイフ、缶きり、ハサミ
□ティッシュ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ
□歯磨きセット、ドライシャンプー
□ビニール袋、ポリ袋
□メガネ予備
□家屋や車の合鍵
□油性ペン
□使い捨てカメラ
【参考】津波対策に役立つページ
▼津波防災マニュアル(石垣島地方防災連絡会・平成16年3月)
http://www.okinawa-jma.go.jp/ishigaki/tmanual/home.htm
▼石垣市・津波浸水予測区域・津波避難場所及び津波避難経路
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/100000/100100/tunamidata/Yosoku.htm
▼石垣市街地の8カ所に「津波避難ビル」の標識
http://www.y-mainichi.co.jp/?action_article_show=true&article_id=5706
▼竹富町・津波浸水予測区域・津波避難場所及び津波避難経路
http://www.town.taketomi.okinawa.jp/gyousei/bousai/bousaihinanbasyo/yosoku.htm
▼Wikipedia:津波(津波に関する基本知識)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E6%B3%A2#.E9.80.9F.E3.81.95
▼琉球大学理学部中村衛研究室(明和の大津波に関する研究)
http://seis.sci.u-ryukyu.ac.jp/hazard/EQ/1771yaeyama/
▼石垣島地方気象台
http://www.okinawa-jma.go.jp/ishigaki/home.htm
▼沖縄気象台
http://www.okinawa-jma.go.jp/
▼気象庁:地震情報
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
Posted by sumao at 23:38│Comments(7)
│島日記
この記事へのトラックバック
地震の前ぶれとして、特有の雲・気象現象が出るといわれています。僕は「地震雲」についてよく知らないのですが、柱状の雲、放射状の雲、赤い月など、阪神大震災の際に見た記憶があり...
地震と空【島の時間 be】at 2007年04月24日 08:25
今日も島の空を見ていました。曇り空のため雲の全容はわからないものの、見慣れない雲はいくつかありました。参考までにここ公開します。撮影:4月25日12時47分 石垣島・真喜良から北...
25日の石垣島の空【島の時間 be】at 2007年04月25日 17:52
この記事へのコメント
ありがとうございます
ワードに貼り付けして 保存しました^^
私も東海大地震の備えとして それなりに準備してありましたが。。。
すべて 処分なり使える物は使ったり 非常食 食べたり^^; 美味くなかったけど
やっぱり 備えあれば。。。と言いますから また近いうちに揃えるか!
ワードに貼り付けして 保存しました^^
私も東海大地震の備えとして それなりに準備してありましたが。。。
すべて 処分なり使える物は使ったり 非常食 食べたり^^; 美味くなかったけど
やっぱり 備えあれば。。。と言いますから また近いうちに揃えるか!
Posted by みっちゃん at 2007年04月22日 16:28
スマオさん、こんにちは。
今週末埼玉に帰省し、そのときに両親と地震と津波の
話をしたばかりで、この記事。あまりのタイミング。
我が家の転居先は兵庫県。記憶にも新しく、スマオさんも
経験された阪神大震災の地でもあります。
埼玉の時には避難バックを準備していましたが
引っ越しでなおざりになっています。
そんなこともあると気を引き締め直し、読ませて頂きました。
今週末埼玉に帰省し、そのときに両親と地震と津波の
話をしたばかりで、この記事。あまりのタイミング。
我が家の転居先は兵庫県。記憶にも新しく、スマオさんも
経験された阪神大震災の地でもあります。
埼玉の時には避難バックを準備していましたが
引っ越しでなおざりになっています。
そんなこともあると気を引き締め直し、読ませて頂きました。
Posted by もきち at 2007年04月22日 17:04
> みっちゃんさん
実は僕も昨日今日でひととおりそろえました。
いざ背負ってみるとやや重いので(笑)
これからどれを最終的に残すか選ぶところです。
何事もないのがベストですが、
何があっても大丈夫な気持ちになれるように。
> もきちさん
偶然ですね。良かったです。
今日また宮古島で地震がありました。
気を引き締めろ、と言われているようです。
大好きな海です。うまくつきあってゆけるはずです!
実は僕も昨日今日でひととおりそろえました。
いざ背負ってみるとやや重いので(笑)
これからどれを最終的に残すか選ぶところです。
何事もないのがベストですが、
何があっても大丈夫な気持ちになれるように。
> もきちさん
偶然ですね。良かったです。
今日また宮古島で地震がありました。
気を引き締めろ、と言われているようです。
大好きな海です。うまくつきあってゆけるはずです!
Posted by スマオ at 2007年04月22日 21:14
とても参考になりました、今マイホームを新築中なのですが、ものすごく低い土地で、(大浜地区~磯辺地区間の国道沿い)ものすごく海に近く、日頃から
津波にはとても興味がありましたが、その矢先の宮古島での地震、津波注意報、小さい子供がいるうえにそろそろ引越し予定なので、大変参考になったと思います、私適に見て引越し予定先から非難する場合、「大浜中学校ぐらいまでは逃げなさい」って子供によく話すのですが、スマオさんからみてどう思いますか?
津波にはとても興味がありましたが、その矢先の宮古島での地震、津波注意報、小さい子供がいるうえにそろそろ引越し予定なので、大変参考になったと思います、私適に見て引越し予定先から非難する場合、「大浜中学校ぐらいまでは逃げなさい」って子供によく話すのですが、スマオさんからみてどう思いますか?
Posted by 石垣大好き! at 2007年04月24日 04:38
> 石垣大好き!さん、ようこそ!
他人事ではありませんね。
防災対策を練るきっかけになれば幸いです。
避難場所について確実なところはわかりませんが、
大浜から磯部は、宮良湾が津波の増幅装置になってしまうので、
宮良方面より大浜方面へ逃げる方がいいのはたしかでしょう。
ただ、明和大津波では、現大浜中学校のあたりまで津波が遡上しています。
万が一の場合は、中学校の屋上でしょうか?
他人事ではありませんね。
防災対策を練るきっかけになれば幸いです。
避難場所について確実なところはわかりませんが、
大浜から磯部は、宮良湾が津波の増幅装置になってしまうので、
宮良方面より大浜方面へ逃げる方がいいのはたしかでしょう。
ただ、明和大津波では、現大浜中学校のあたりまで津波が遡上しています。
万が一の場合は、中学校の屋上でしょうか?
Posted by スマオ at 2007年04月24日 10:16
スマオさん、こんばんは。
初めて訪れたサイトでしたが、美しい自然に囲まれた素敵な空間ですね。
八重山の大自然のほか、島人のお人柄の良さが存分に伝わってきます。
雲についてのご質問をいただきましたが、雲サイトを運営こそはしておりますが、「地震雲」というもの自体には実は「懐疑的」なんです(笑)。
自然が見せる現象を、人間が勝手に「普通の雲」や「地震雲」と決め付けたように分類してしまうのって、おかしいでしょ?
20日の宮古M6.7他は、大きな被害とならずに、幸いでしたね。
個人的には、震源近い位置での現象(色調整?)として、19日夕と20日朝の画像には、大変興味を持ちましたよ。
初めて訪れたサイトでしたが、美しい自然に囲まれた素敵な空間ですね。
八重山の大自然のほか、島人のお人柄の良さが存分に伝わってきます。
雲についてのご質問をいただきましたが、雲サイトを運営こそはしておりますが、「地震雲」というもの自体には実は「懐疑的」なんです(笑)。
自然が見せる現象を、人間が勝手に「普通の雲」や「地震雲」と決め付けたように分類してしまうのって、おかしいでしょ?
20日の宮古M6.7他は、大きな被害とならずに、幸いでしたね。
個人的には、震源近い位置での現象(色調整?)として、19日夕と20日朝の画像には、大変興味を持ちましたよ。
Posted by ゴロウ at 2007年04月26日 01:08
> ゴロウさん、ようこそ!
アドバイスありがとうございます。
たしかにいたずらに「地震雲」という見方をしてしまうのは危険ですね。
上空が動いている、というぐらいの理解かもしれません。
島の近海でまた地震活動が起こっています。
揺れを感じないからと安心せず、注意していきたいと思います。
もちろん、被害が出ないことを祈りながら。
アドバイスありがとうございます。
たしかにいたずらに「地震雲」という見方をしてしまうのは危険ですね。
上空が動いている、というぐらいの理解かもしれません。
島の近海でまた地震活動が起こっています。
揺れを感じないからと安心せず、注意していきたいと思います。
もちろん、被害が出ないことを祈りながら。
Posted by スマオ at 2007年04月26日 11:04